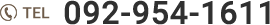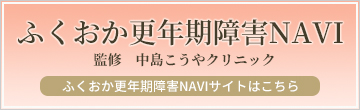点滴療法
マルチビタミン・ミネラル点滴(マイヤーズカクテル)

■ マイヤーズカクテルとは
マイヤーズカクテルとは、アメリカのマイヤー医師が、慢性疲労、喘息、うつなどの患者に対して30年以上にわたって行っていたビタミンとミネラルの点滴を、ゲイビー医師(アメリカホリスティック医学協会元会長)が現代医学のエビデンスに合わせて再現したもので、定番のマルチビタミン・ミネラル点滴です。
ビタミンB群(B1・B2・B3・B5・B6・B12)とビタミンCを、硫酸マグネシウム、グルコン酸カルシウムとともに、100ml生理食塩水(または5%糖液)に入れ、30分以内で点滴します。マイヤーズカクテルの効果は、栄養素としてのビタミンB群、ビタミンC、マグネシウム、カルシウムの作用によるものです。必要な栄養素を静脈内に直接投与するため、経口摂取に比べて確実に血中濃度を上昇させることができ、細胞内にもより効果的に行き渡ります。
■ マイヤーズカクテル点滴療法の適応
マイヤーズカクテルには、下記示すようなさまざまな症状や疾患に対する効果が経験されています。
気管支喘息、片頭痛、慢性疲労、線維筋痛症、うつ状態、運動パフォーマンス、上気道炎、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、慢性蕁麻疹、耳鳴り、こむら返り 甲状腺機能亢進症、心臓病
■ マイヤーズカクテルの副作用
血圧低下、低血糖、アレルギー反応、アナフィラキシーショックが起こることがあります。
■ 文献
Gaby AR. Intravenous Nutrient Therapy: the “Myer’s Cocktail.” Altern Med Rev 2002;7(5):389-403
高濃度ビタミンC点滴

■ ビタミンCの働き
ビタミンCには次のような作用があります。
- ①抗酸化作用
- ②酸化作用(点滴大量投与)
- ③コラーゲンの構築
- ④カルニチンの合成
- ⑤アドレナリンの合成
- ⑥鉄の吸収促進
- ⑦免疫力の亢進(貪食、インターフェロン産生、T細胞成熟)
- ビタミンCには、抗酸化作用、コラーゲン構築作用があるため、骨や筋肉や皮膚の老化を防ぐ効果があります。また、ビタミンCは血液脳関門を通過するため、抗酸化作用により神経細胞やグリア細胞を保護し、アルツハイマー病の予防効果が期待できます。
- 大量投与(超高濃度ビタミンC点滴)では、ビタミンCは逆に酸化物質となり、がん細胞を殺す作用が生まれます。
- アドレナリンの合成作用、鉄の吸収促進作用があるため、疲労感やメンタルに良い影響を与えます。
- 白血球の機能亢進作用があるため、感染症の防御効果があります。
- ビタミンCの摂取量はテロメアの長さと相関しており、ビタミンCの摂取はアンチエイジングにも効果が期待できます。
■ がんに対する高濃度ビタミンC点滴の効果のメカニズム
高濃度ビタミンC点滴療法とは、通常の摂取量よりもはるかに大量のビタミンCを点滴投与する治療法です。正常な細胞にはほとんどダメージを与えず、がん細胞だけを選択的に死滅させることができるため、副作用の非常に少ないからだに優しいがん治療法として注目を集めています。
ビタミンCを大量に点滴投与すると、血液中や細胞周囲で大量の過酸化水素が発生します。過酸化水素は、酸化作用により細胞内のミトコンドリアやDNAにダメージを与え、細胞を死に至らせます。正常な細胞は、カタラーゼやグルタチオンペルオキシダーゼという抗酸化酵素が働き、過酸化水素を分解して無毒化してしまいますが、過酸化水素を分解する抗酸化酵素が少ないがん細胞は、過酸化水素を分解することができないため、細胞が障害を受けて死滅してしまいます。このように、ビタミンCは正常細胞にはあまり影響を与えず、がん細胞だけを選択的に死滅させることができると考えられています。
■ がんに対する高濃度ビタミンC点滴療法の適応
がんに対する治療は標準治療を優先させるべきですが、高濃度ビタミンC点滴療法は、通常の抗がん剤治療と比べて副作用がほとんどなく、QOLの改善が期待できますので、がん治療の補助療法として用いられています。
- ①標準治療が無効で、他に有効な治療法がない場合
- ②標準治療が副作用で続けられない場合
- ③標準治療の効果を高め,副作用を和らげる(標準治療との併用)
- ④良好な体調を維持しながら寛解期を延長させる(再発予防)
- ⑤手術までの待機期間中の治療(術前治療)
- ⑥標準治療を拒否し,代替療法による治療を希望する場合
■ がんに対する高濃度ビタミンC点滴療法の実際
がん細胞を死滅させるのに必要なビタミンCの血中濃度は、350~400mg/dl以上といわれており、この濃度を実現するためには、通常1回50g以上の大量のビタミンCの点滴が必要になります。がんに対する高濃度ビタミンC点滴療法は、アメリカのリオルダン医師によって確立されました。国内でも、リオルダンのプロトコールに沿った方法が、安全なプロトコールとして用いられています。
- 1.G6PD活性値を測定し、高濃度ビタミンC点滴療法の禁忌でないかを調べます。
- 2.15g→25g→50g→とビタミンCの点滴量を増やしていきます。
- 3.ビタミンC血中濃度を測定し、維持量を決定します。
- 4.最初の6ヶ月は週2~3回、その後6ヶ月は週1回、以後月1~2回点滴します。
■ がんに対する高濃度ビタミンC点滴の注意事項
- 禁忌: G6PD欠損症、高度の腎不全および心不全の場合はできません。
- 併用薬注意: メトトレキサートの投与前24時間、投与後48時間以内の高濃度ビタミンC点滴は禁忌です。
- 慎重投与: ビタミンC点滴製剤にはNaが含まれていますので、胸水、腹水、浮腫を悪化させる恐れがあります。
- 副作用・リスク:腫瘍壊死・出血・発熱、吐気・頭痛、血管痛、低Ca血症、低血糖、打撲部位の内出血などが起こることがあります。
EDTAキレーション
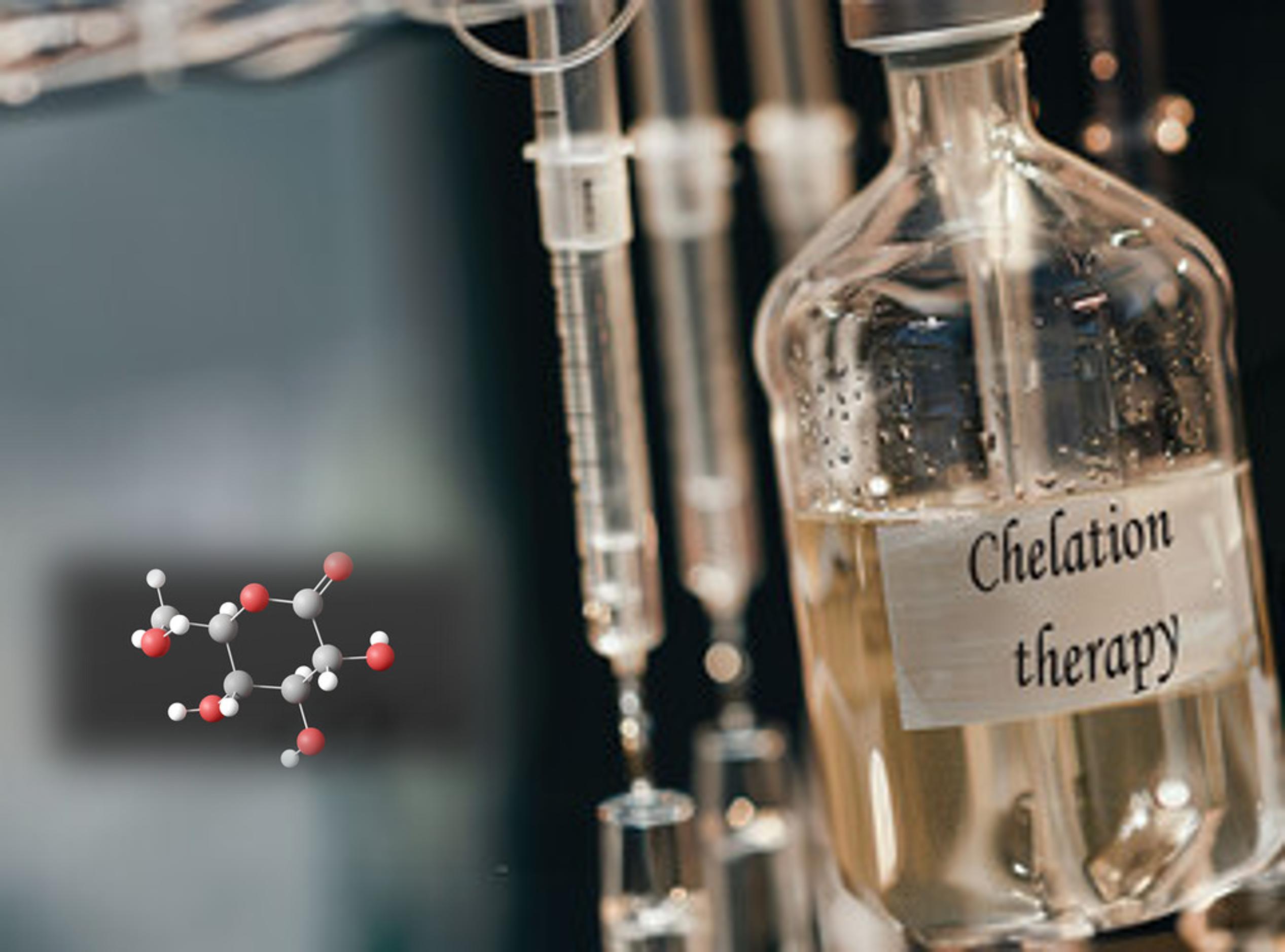
■ キレーション治療とは
私たちは、環境汚染、食品汚染にさらされており、体内にはさまざまな不純物や有害金属が蓄積されています。不純物や有害金属が体内に蓄積すると、活性酸素が増え、酵素活性や神経や血管に悪影響を与えます。その結果、いろいろな不定愁訴が生じ、動脈硬化(血管の老化)が進行する原因になります。
体内の有害物質は、尿や汗となって体外に排泄されますが、点滴や内服によって積極的に有害物質を除去し、不定愁訴や老化の進行を食い止めようというのがキレーション療法です。有害金属を除去する薬剤は、カニのはさみ(キール)のように重金属をつかんで体外に排泄させるため、キレーションという名前がついたと言われています。キレーションには、EDTAやDMPSによる点滴療法と、DMSAやDMPSによる内服治療があります。
■ EDTAキレーション
EDTAキレーション療法は、目的によって大きく2つに分けられます。主として動脈硬化(血管の老化)の予防・治療を目的とするNa2-EDTA(=Mg-EDTA)と、有害金属の排出を目的としたCa-EDTAです。
EDTAキレーションの動脈硬化に対する治療は、鉛中毒の患者にEDTAキレーションを行ったところ、狭心症の症状が改善したという発見から始まりました。その後、症例が積み重ねられ、EDTAキレーションによって、虚血性心疾患に対する心臓バイパス手術を避けることができたり、閉塞性動脈硬化症に対する下肢切断を避けることができるという効果が明らかにされました。狭心症や間欠性跛行などの自覚症状の改善、心機能の改善、脳血流の改善、血管年齢(PWV)の改善なども報告されています。EDTAキレーションは、下記の疾患に対して試みられていますが、主な作用機序としては、有害金属の除去による酸化ストレスの改善が考えられています。
EDTAキレーションは、アメリカでは年間約80万件行われておりますが重篤な副作用はなく、点滴速度を守り(90分かけて点滴します)、ACAM(アメリカ先端医療会議)の方法に従って行えば、安全性に関しては問題ないと考えられます。2002年から2011年にかけて、米国国立衛生研究所で、心筋梗塞の再発予防に対するEDTAキレーションの効果を検討する大規模臨床試験が行われ(TACT試験)、EDTAキレーション治療群では、死亡や重症心血管事象の頻度が有意に低下したという結果が得られています。
■ EDTAキレーション療法の適応
| ①動脈硬化の予防・治療 | 虚血性心疾患・ 閉塞性動脈硬化症 |
|---|---|
| ②有害金属の排出 | 鉛・カドミウム・アルミニウム・水銀・ヒ素 |
| ③神経変性疾患 | パーキンソン病 アルツハイマー病 |
| ④眼科疾患 | 加齢黄斑変性症 |
| ⑤膠原病 | 強皮症 |
| ⑥皮膚疾患 | 乾癬 |
| ⑦アンチエイジング | フリーラジカルによるダメージ しみ しわ |
■ EDTAキレーション療法の実際
- 1.EDTAをビタミン剤とともに週1回90分かけて点滴します。
最初は、症状に応じて週2回行うこともあります。 - 2.3ヶ月(10回)ごとに効果判定を行い、症状に応じてこれを数クール繰り返します。
- 3.Ca-EDTAでは、尿誘発試験により重金属の排出状況を判定します。
Na2-EDTAでは、血液検査、血圧脈波検査、頸動脈エコーなどで動脈硬化の評価を行います。 - 4.6ヶ月程度行った後、効果が確認できれば月1~2回に減量します(維持療法)。
キレーションによる副作用を減らし、効果を高めるために、ビタミンやミネラルなどのサプリメント(内服)を併用します。
■ EDTAキレーションの注意事項
- 禁忌:妊婦、急性鉛中毒、高度の腎機能異常・うっ血性心不全・肝機能異常では禁忌です。
- 副作用・リスク:腎障害、静脈炎、低Ca血症、低血圧、低血糖、疲労感、不整脈、内出血、アレルギー反応などが起こることがあります。
オゾン療法
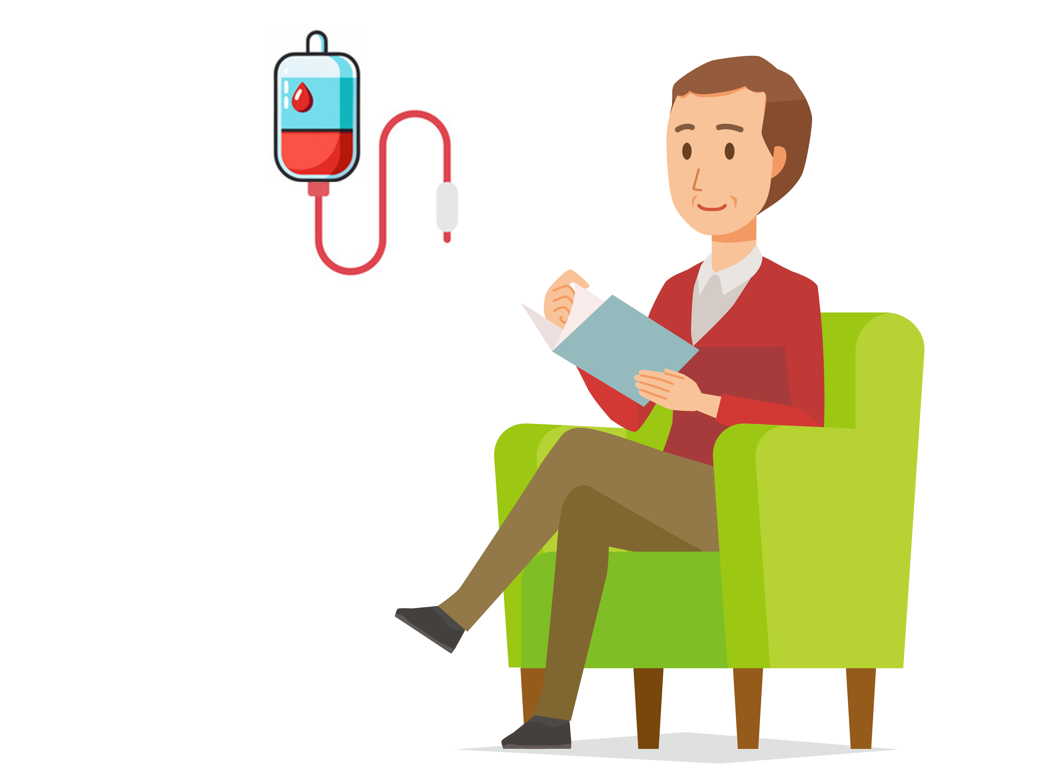
■ オゾン療法とは
オゾン療法とは、患者さんから採取した血液に活性酸素であるオゾンを反応させた後に、点滴で患者さんの血中に戻す治療法です。身体に害のない程度の酸化ストレスを与えて自分の抗酸化力を高めるホルミシス効果を利用した治療法です。さらに、オゾン療法には全身の酸素化という効果もあります。
オゾン療法には次のような作用があります。
- ①抗酸化力を高める
- ②炎症を抑制する
- ③免疫機能を活性化する
- ④血液循環を改善する
- ⑤ミトコンドリア機能を高める
■ オゾン療法の効果が報告されている症状・疾患
オゾン療法には次のような症状や疾患に対する効果が報告されています。
| ① 虚血性疾患 | :虚血性心疾患、下肢閉塞性動脈硬化症、糖尿病性壊疽 |
|---|---|
| ② 疼痛 | :線維筋痛症、変形性膝関節症、腰椎椎間板ヘルニア |
| ③ 疲労 | :慢性疲労症候群 |
| ④ 神経疾患 | :多発性硬化症、パーキンソン病、突発性難聴、耳鳴り |
| ⑤ 感染症 | :Covid-19 |
| ⑥ がん | :乳癌、放射線療法の副作用軽減、緩和医療 |
| ⑦ 歯科領域 |
■ オゾン療法の方法
- 1.100mL血液を採取
- 2.オゾン発生器で血液とオゾンを反応させる
- 3.オゾンと反応した血液を点滴で血管内に戻す
■ オゾン療法の注意事項
- 禁忌: 妊婦、G6PD欠損症、甲状腺機能亢進症、急性冠症候群、脳梗塞急性期、出血傾向
- 副作用: 点滴による皮下血腫・神経損傷、オゾンによるだるさ、抗凝固剤によるアナフィラキシー・出血・血小板減少・しびれ等が、まれに起こることがあります。
Anti-Aging 治療
- 再生医療
-
診療内容
項目 説明 保険診療 内科、胃腸科、循環器科
呼吸器科、禁煙外来
男性更年期外来、女性更年期外来自由診療 サプリメント栄養療法
ナチュラルホルモン補充療法
キレーション療法
高濃度ビタミンC点滴療法健診、ドック 健康診断、人間ドック
アンチエイジングドック -
診療時間
外来診療時間 月 火 水 木 金 土 9:00~12:30 ○ ○ ○
13:00まで○ ○ ○
13:00まで14:00~18:00 ○ ○ ○ ○ ※受付時間は診療時間の20分前までとなります。
※健診受付は午前10:00~11:30です。予約状況を事前にお問い合わせください。
※発熱外来の時間は、新型コロナウィルスの流行状況により変更になる可能性があります。
休診日:日曜日、祝祭日、年末年始、お盆休み
-
アクセス
新幹線博多南駅徒歩1分
〒811-1213
福岡県那珂川市中原2-127博多南駅前医療ビル2F